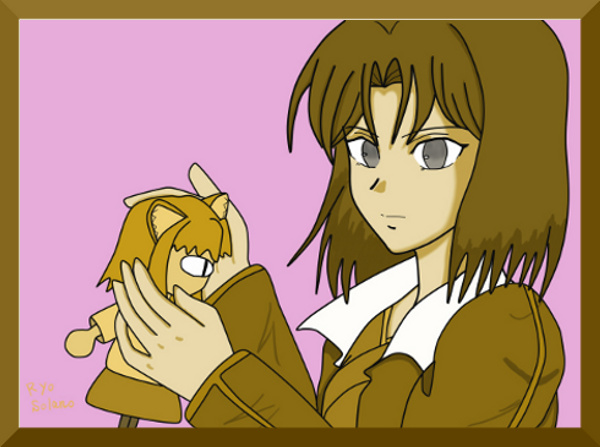空の境界
──変わりゆく日常──
「両儀式と買い物」(後編)
(其の壱)
だいぶ空が怪しい。御上が言うには夕方以降、雨か雪になるかもしれないという。気温も到着直後より下がっているようだ。吐く息がずっと白い。私はあまり寒さや暑さは感じないのでどうってことないが、私を買い物に引き込んだ男は寒いのが苦手であるらしい。
「なんか雪が降りそーな感じです」
といかにもさむそーにつぶやき、背中を丸めてくしゃみを連発した。
──1998年12月22日 15時30分──
クリスマスパーティー用のなんたらかんたらを買い終えた私こと両儀式と伽藍の堂の新顔の御上真は、購入したパーティーグッズを車に置き、大手おもちゃチェーン店を目指して大通りを徒歩で北上していた。目的はビンゴゲーム用のプレゼントだという。
「なんでもいいじゃん」
と私はめんどくさそうに言ったのだが、
「だめです」
ときっぱり拒否されてしまった。この男、幹也と同じで妙に頑固なところがある。
「とりあえず6人の予定ですから、6人分必要なわけです。もちろん、6人が6人とも同じ価値観ではありません。ただのビンゴゲームのプレゼントなんだからなんでもいいじゃん、とか思いがちですが、どうせならもらって嬉しいもの、役に立つものがよいに決まってます。女性も4人もいることですしねー」
私は、この男のこだわりを殺すことはできない。私がとやかく言うことでもないだろう。
ふと、私はある疑問に気が付いた。
「おい、御上。なんで6人なんだよ。トウコの事務所に出入りするのは鮮花をふくめて5人だろ?」
私が疑問をぶつけると、少し先を行く背の高い男は立ち止って振り向いた。
「ああ、そのことですか、まだ確定ではありませんが浅上さんが来るかもしれないんですよ」
私は驚いて立ち止まってしまった。
「なに!?浅上、浅上って浅上藤乃のことか?」
「はい、そうです」
御上の肯定はごくさりげない。私と闘り合ったあの危ない女をパーティーに誘うというのか?
「まあ、あれから数ヶ月が経ったわけです。おとといですが偶然、鮮花さんと一緒にアーネンエルベにいるところを会いまして、黒桐を交えていろいろ話をしました。傷は癒えたようですが、まだまだ精神的には立ち直れていないみたいでした。たぶんそのことがあったからでしょう、橙子さんが鮮花さんに連絡した折に浅上さんもどうかっていう提案をしたんですよ」
私は黙って聞いていた。なるほど、あの浅上藤乃がねえ。今年の10月に学園に復帰したところまではトウコに聞いたが、私にとってはもう終わったことだった。あの女がその後なにをしようと知ったことではないが、まさかこちらの日常に入ってこようとしているとは意外だった。ふん、別に呼ぶなら呼ぶでどうでもいいことだ。来たら来たで面白いことになりそうだ。
それにしても、トウコや幹也とは違う意味で異質なこの男の思考はよくわからない。
(ああ、そういえば)
私は思い出してしまった。
「おい御上、お前、浅上藤乃に土下座したんだってな」
男の顔がみるみる高揚し、それは動揺のまなざしに変わった。赤みがかかった髪がさらに色を濃くしたように見えた。
「ちょっと・・・いったい・・・誰から聞いたんですか?」
面白い反応だ。口調が途切れ途切れだ。最近、この男のペースに巻き込まれぱなしなので、これはこれでよい機会だ。
「さあね。だれかな?」
「あっ!幹也のやつか、あいつ、式さんにはしゃべりそうだ」
「いや、トウコからだぞ」
「はっ!?なぜ橙子さんが知ってるんだ!」
知らないよ、と言ったら御上は真剣に考え込んでしまった。きっといくつかの容疑者を思い浮かべたはずだが、私はそれがすべて外れになることを知っている。久々に私は饒舌になったと思う。
「お前、浅上に土下座した上にあの女を守ってやるとか言ったそーじゃん」
長身で鍛え抜かれた男の身体がよろめいた。その若い騎士のような顔は引きつっており、すぐにでも地面に倒れ伏しそうだった。御上は力のない声で私に尋ねた。
「式さん、どこまで聞いているんですか?」
「ほとんど全部」
と言ってやった時のあいつの顔は傑作だった。おそらく魔眼の力を使えば容易に真相を知ることができるだろう。そうしないのはどうにもならない場合を除き能力を封印しているからだった。強力な魔眼を有しながらそれに頼ることを潔しとしないのだ。風の力を使う少年と戦ったときもせいぜい数回しか発動させていないはずだ。
全く理解できない考えなのだが、この男は本来人が持つ「思考・判断・洞察・推理・想像」といった能力の可能性を信じており、人外的に有する能力を嫌っている。だから、御上真は時に遠回りをしてまでも超能力を使わずに事の真相にあたろうと動き、失うべきものでないものを失うときがある。
私は、歯がゆく感じるときもあるのだが、なぜかこの男のする事をとがめることはできないでいる。
だからこそ、御上は浅上藤乃に会った時、浅上の心情を能力で知ろうとせず、実際に話し、尋ね、考え、質問することでその内側を知ろうと努力したのだろう。だからこそ浅上藤乃は御上真という男に心を開いたのだ。
と私はある人物から聞いていた。
御上が伏せていた顔を上げた。
「まあ、大それた事をしようとは思いません。できもしないでしょう。浅上さんの心はまだ閉ざされているのは確実です。彼女は罪を背負って生きていくでしょう。ですが、今のままでは彼女は同じ過ちを繰り返すかもしれません。浅上さんが支えにしている人がいるにせよ、その人が彼女のものにならない限り、内にこもるこれまでと大して変わらない存在に対して実感できない生活を送ることになるでしょう。
俺はね、彼女には罪は罪として受け入れてもらい、逆に彼女にはもっと前向きに、人並みの幸せくらいはつかんでほしいのですよ。そのための手助けをしたい、それだけです」
「なるほどね」
この男は幹也以上のお人好しだと私は思った。浅上藤乃の犯した罪に対して負い目を感じることなど一切なくてよいはずなのだ。藤乃自身が同じ事を言ったと私は聞いている。
しかし、御上は視えていたのに行動しなかったことを悔いており、自分が関わっていればもう少し違った結果になったのではないかと自分を責めている。
残念だが私はそうは思わない。過程は違ったかもしれないが、結果は同じだったと思う。浅上藤乃は痛みを知ってしまったときから箍が外れてしまったのだ。内に潜む狂気が暴走し、人が肉塊に変わっていく有様を薄ら笑いを浮かべて見物していたのだ。私が戦わなかったのなら、御上が浅上藤乃と戦っていただけのことだ。そしてその結果は最悪になっていたことだろう。御上は浅上藤乃の病気を殺すことができないからだ。
あの事件以来、もちろん浅上藤乃には会っていない。会いたいとも思わない。そんな女の力になりたいだなんて、何を考えているんだか。まったく幹也のやつと同じだ。
ある意味、幹也と御上は共通の特性を持ち合わせている。「異」なるものを引き寄せる力があるということだ。(トウコ談)幹也は捜す前にすでに浅上藤乃に出合っていたし、御上は知る前に浅上をすでに知っていたのだから。
なんという共通点だ。ただ深刻度という点では御上真のほうが幹也より「上」におもえてならない。
私は忠告した。
「おい、浅上にあまり入れ込むのはよせ。あの女は危ないからな」
どうして御上真は奇妙な顔をしたのだろう。何か不審なことでもいったのだろうか?私にはわからない。一つだけわかったのは、ふと気が付くと目的の場所に着いていたという間違えのない認識だった
(其の弐)
トイショップに入る前から「混んでいる」という印象はあった。なぜなら、店舗の入り口に通じる10段ほどの階段を親子連れやお父さんやお母さんやらが次々と上がっていくからだった。
「さすがにクリスマス前だなぁ」
俺が階段の手前で悠長につぶやいていると、またもや「カラン」と音がして着物姿・・・なんだけど革のブルゾンをまとった両儀式が華麗にしてさっそうと階段を上っていく。
「おい御上、はやくしろ。今何時だと思っている」
怒られてしまった。
「はい」と答えて思わず敬礼してしまう俺は何者?
いや、まてまて、ちがうぞ。なんだ、この式さんの積極性は?
「とっとと終わらせて次に行くぞ。めんどー事はまだあるんだろう?」
そうだよなぁ、トイショップに興味があるわけじゃあないよな。早く終わらせたいよなぁ・・・
しかし、俺はハッとした。めんどーでも式さんは自分からトイショップに足を踏み入れようとしている。普段なら絶対にありえない行動だ。いやなら嫌で近づきもしない場所であるはずなのだ。もしかしたら彼女はショップに入ってみたいのではないだろうか?もちろん、一人で入るのは気が引ける。黒桐とは恥ずかしくて論外だろう。
そこで推察だが、実行委員長の俺とパーティー用のプレゼントやらを橙子さんに命じられて購入しに来たという立派な理由がある場合はどうか。それは式さんが望んだことではなく、あくまでも付き添いの過程で仕方のないことだという理由であれば、彼女はそれを隠れ蓑にして堂々とショップに足を踏み入れることができるのではないか?
「邪推というよりもーそーに類似した考えだな」
単なる早とちりで終わるか、世紀のスクープ(伽藍の堂関係の人限定)となるかはショップに入ってみればわかることだった。
「混んでいるなぁ・・・」
やはり予想は当たっていた。このショップは周辺では有数の売り場面積と品揃えを誇っている。それが一階だけでクリスマス前の平日とは思えないほどお客さんがいる。
「明日の祭日はもっとひどいな・・・」
とりあえず、今日来ておいて正解だった。まだまだゆっくりまわれる空間はある。
トイショップは2階建てだ。1階は今や大人気のTVゲームやPCゲーム関連の商品とボードゲームやトランプなどのアナログゲームの売り場だ。2階はプラモデル、モデルガン、フィギュア、ぬいぐるみ、人形の売り場だ。マニアよだれものの逸品も少なくないらしい。
「ゲームかぁ、俺以外にゲーム機もってる人はいないけど・・・見るかな」
ついでに最新のファイナルファンタジーでも買っておこうか?
「式さん、ちょっと1階も見ていきます」
ふと、隣を見ると彼女がいなくなっている。
「あれ?」
やばい、俺がぼーっとしている間に彼女は俺に話しかけたが、妄想段階に入っていたのであきれてどこかに行ってしまった可能性が高い。幸いなことに外に出たわけではなさそうだ。店内のどこかにいるようだ。こうなるとさっきの妄想がますます現実味を帯びてくる。
「とりあえず見ながら捜すかな」
しかし、5分も経たないうちに両儀式を見つけてしまった。しかもTVゲームのデモプレイコーナーの一角で、小学生と一緒に格闘ゲームに興じている「あの両儀式」に遭遇してしまったのだ。
俺はとっさに隠れてしまった。そしてこっそりと様子を伺いながら自慢のニコン一眼レフカメラを持って来なかったことを本気で後悔した。妄想が現実になるとは意表を突かれた格好だ。
「幹也に見せてやりたかったぜ」
鮮花さんがいたら世紀のスクープ(絶対に)をビデオに収めただろうか?
再び式さんを見た。ゲーム機の前に小学生とおぼしき少年3人に囲まれる?状態でそのうちの一人と対戦している。というよりやらされているのか?てきとーにボタンを押しているように見える。始まってからすぐに正拳突きを立て続けにくらい、最後は必殺技でトドメめをさされていた。その間、わずか60秒・・・
やや後方からなので表情をうかがい知ることはできなかったが、負けたあとになにやら少年に話しかけるとゲームを再開した。
「おおっ」
と思わず唸ってしまったのは、さっきよりも各段に操作が上達していることだった。ちゃんと相手の攻撃に対応し反撃ができている。なるほど、前の対戦は操作方法が不慣れだったのであっさり破れたのだろう。リベンジしたわけだ。それにしても2回目であれだけ動かせるとは式さんは飲み込みが早い。
しかし、どうしても経験値の差は大きく、土壇場で必殺技を連続で食らってしまって負けた。
「おしい!」
とつい声に出してしまったのはまずかった。すぐに反応した式さんとモロに視線が合ってしまう。俺はとっさに口笛を吹いて・・・などという古典的な方法でごまかしたが、もちろん有効であるはずがない。式さんは迫力のある眼差しで俺の前に立った。
「御上・・・」
「は・・・い・・・」
とうぜんドッキドッキだ。
「いるんなら声くらいかけろ」
声に恥ずかしさがこもっていた。最後に「チッ」と舌打ちしたのはやはり見られたくなかったからだろう。俺は笑って言った。
「まさか式さんがゲームしているとは思わなくて・・・どういういきさつでそうなったんですか?」
特に返答を期待していたわけではなかったが、式さんはブルゾンのポケットに両手を突っ込んだまま、やや視線をそらしてポツリとつぶやいた。
「たんなる成り行きだ・・・」
一体、どういう法則で小学生とゲームをすることになったのだろう。真相を知りたくなったが式さんの機嫌を損ねるのもまずいので突っ込みは自重し、2階に向かうことを告げてその場を後にした。去り際、式さんは小学生に軽く手を振って別れ、小学生たちも彼女に応えるように手を振り笑顔で見送ってくれた。このままだと式さんと小学生の間に起こった奇蹟は永遠に謎となってしまうのだろうなぁ・・・
2階に上がった。相変わらず式さんはクールな表情で俺の後ろを歩いてくる。一緒に来てくれるだけありがたい。俺は12月の事件を式さんと追う過程でずいぶん彼女と打ち解けたと思う。他人を寄せ付けない、または寄り付かないこのきれいな女性が俺に少なからず心を開いてくれたのは事件の事もあるが、彼女とかつて奇妙な共同生活をした臙条巴という少年と雰囲気が似ていることもあったのだろう。
なるほど。それは否定できない。臙条巴を脳裏に思い浮かべたとき、奇妙な既視感を味わったものだった。
そして、彼の行動と勇気が両儀式を救ったことに感銘を受け、同時に自分に自己嫌悪すら覚えたものだった。もちろん、勇気をだせず踏み出せなかった自分にだ。
いずれにせよ、時間が少したってしまったが、今の現状は臙条巴のおかげといえるだろう。御上真は彼の思いを受け取り背中を押されたようなものだから。
「おい、御上。ここで何を買うんだ?」
「そうですね。特に決めてないので、ちょっと見回ってから買いますよ」
「なんだ、けっこうめんどくさいヤツだな。ゲームのプレゼントなんか何でもいいだろ」
俺は首を横に振った。
「さっきも言いましたが、なるべくもらって嬉しいものにします。本人の希望とあっていなかったとしても、別のものを当てた人と交渉しだいでは交換できますからね。でもてきとーにしすぎると、どちらもその価値がない場合、交換できる余地もありません。低予算ですが、ある程度もらって嬉しいものにしないとだめなんですよ」
ここはきっぱりと妥協しない旨を明確にすると、両儀式は多少不満な顔をしたが、「わかったよ」とつぶやいてそれ以降は何も言わない。
とはいえ、売り場を一周した結果、結局、店の最大の名物である「ぬいぐるみ」に決定した。このショップのぬいぐるみ売り場は他のショップや支店の売り場面積を軽く凌駕しており
「県下ナンバー1」と宣伝するほどなのだ。
ほどなくしてぬいぐるみを物色し始めたが、案の定、式さんのノリはいまいちだ。それでも様々なぬいぐるみを見るたびに「こんなものを喜ぶヤツの気が知れない」とか「何か役に立つのか」など、一応は感性に訴えるだけの刺激はあるようだった。
「ぬいぐるみかぁ・・・」
俺が考え込んでしまったのは、目下のところぬいぐるみを喜ぶ人物が「2名くらいしかいないのではないか?」と気づいてしまったからだ。黒桐鮮花、浅上藤乃のことだ。
この2人は間違いなく喜んでくれるはずだ。当然、吟味は慎重に行うべきである。まあ、ダイレクトに当たらなくても、2人以外に当たった場合は交換される可能性が高い。
そして蒼崎橙子の場合だが、この人もどう想像してもぬいぐるみを抱いていると言うのか飾っているという光景が全くといってっもいいほど浮かんでこない。いや、これは師に対する偏見とでも言うのか、案外、かわいいものが好きだったりして・・・
「きっと、効力のある呪い人形なら大喜びしたかな?」
だめだ、考えが脱線してしまう。いくらなんでも「かわいいぬいぐるみ」からは逸脱してしまう。そういえば千利の実家に依頼で預かっているそんな人形があった気がする。
で、式さんはどうかというと、彼女もほぼ絶望的だ。
俺は、式さんを一瞥した。彼女の部屋に一体くらい「かわいいぬいぐるみ」があってもいいと思うが、当人は全くと言っていいほど興味がないことだ。
・・・と普通は誰しも思うだろう。
しかし、さりげなく式さんの方向にふり向いた俺はゲームコーナーの式さん以上に驚く光景を目撃してしまった。なんと彼女は一体のぬいぐるみを両手にもったままずっと眺めているのである。
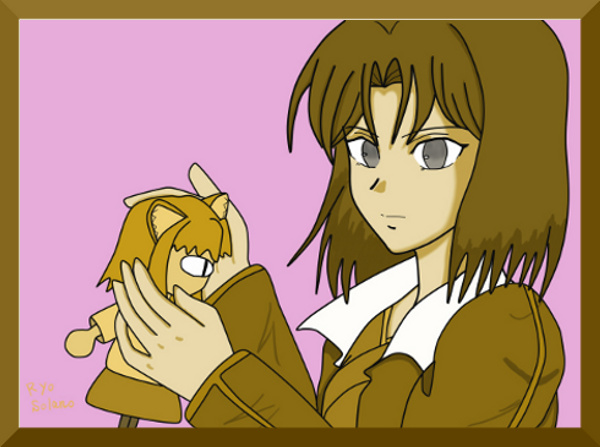
俺は、意味もなく周囲を警戒してしまったが、これは幾分動揺したからだと思う。反射的に身を隠し・・・身を隠した場所は完全に死角になっていたが、我慢できずに「透視」を発動した。
「えっ?」
俺が視たものは、「ネコアルク」をじっと見つめている式さんだった。最近、某CMキャクターとしてちまたで人気が急上昇中だ。俺の周囲、いわゆる大学でも「ネコアルク」の人気は高まりつつあり、カバンやバックに小さめの人形を付けている女子学生が多くなっている。かくいう俺の妹もそのぬいぐるみと携帯ストラップとキーホルダーを持っている。(俺のカバンにも一体付いている)つぶらな大きな瞳とどこか不遜な顔がなんとなく人気のようだ。知り合いの話だと何かの女性キャラの擬人化ということだが、詳しくは知らない。
「式さんは、わりと一般的な感覚を持っているのかもね」
いや、ちがうだろう。式さんが「ネコアルク」のことを知っているとは思わない。これはインスピレーションか、はたまた何かの直感的感性が引き起こした「突然変異」とでもいうのか、スクープ第2弾だと思う。
式さんは、たっぷり7分ほどコーナーを物色し、「着物アルク」を棚に戻すと周囲をキョロキョロと見回した。たぶん、俺を捜しているのだろう。今が出て行くチャンスと捉えた。
「式さーん、ここにいましたか、何か気に入ったものはありましたか?」
完璧なタイミングだ。彼女は透視されていたことには気が付いていない。慎重を喫し、距離をとったことも幸いしたのだろう。式さんに気づかれずにやり過ごすというのは非常に困難なことなのだ。
「あるわけないだろう。そっちこそ買うものは決まったのか?そろそろ16時半になるぞ」
ええ、そうですね、と答えつつ「ウソついちゃって」と内心で笑う。ここで一芝居だ。もう少し見ますと告げておいて「ネコアルク」の棚をごくごくさり気なく発見するのだ。
「これって最近流行ってるキャラですねー、へえ、ぬいぐるみもこんなに種類が出ていたんだ」
と言って、俺は式さんが一番長くガン視していた「着物アルク」をおもむろに手に取る。
「このタイプは珍しいですね。そうだ、プレゼントに一つはこれにしよう。どうです?式さん」
「なぜ俺に聞くんだ。お前がいいと思うものを買えばいいじゃないか、いちいちオレに言うな」
予想通りの発言だ。式さんは興味なさ気に顔を背けたが、一瞬だけこっちを見た。俺は気が付かないフリをして言った。
「じゃあ、これ買います」
俺は、スタスタとレジで会計を済ませた。その過程で両儀式の微妙な百面相は一生記憶に残ると思う。
「さて、じゃあ、次にいきましょう」
「次って?」
「もちろん、残りのプレゼントです。次はハ○ズに行きます。そこで全部そろいます」
「ここで揃うんじゃないのか?」
やや呆れ顔の彼女の表情も「いいなぁ」と思いつつ、俺は告げた。
「まさか、ぜんぶおもちゃにしませんよ。次はもう少し実用的なものを買います」
式さんが形のよい眉をしかめて問うが、もちろん秘密にする。
「ついてくればわかりますよ」
俺は、式さんの背中を押した。
「えーと、安眠枕に温泉の素、あとは手帳だな」
ハ○ズに到着してから順調に買い物を進め、残りは一つになった。手帳というのはありきたりの気がしたが、橙子さんや幹也には来年の物が必要と考えたのだ。橙子さんでさえ手帳は使っていたし、幹也は何かとめんどーごとをやらされているのでスケジュール管理は特に細かい。地味かもしれないがこれ以上のものはない。あとはどちらかがすんなり当ててくれることを願おう。
文具売り場に着いた。一角にクリスマス関連のコーナーが設けられていて、そこには大勢の人が集まっている。ちょっとのぞいてみると・・・なるほど。
まず目的を達成することにした。式さんは特に何も言わず、時折、文具を手に取りながら何気に売り場を見ている。俺はそれを横目に見ながらデザインのよさと書きやすさ、見易さの条件が揃ったやや高めの手帳に決めると、先ほど人が集まっていたコーナーに赴き、サンタやトナカイ、ゆきだるまのイラストが入ったクリスマスカードを5枚選んだ。
「どうするつもりだ?」
横から声をかけてきたのは式さんだった。どうやら興味があるらしい。俺は選んだカードを広げて彼女に見せる。
「ゲーム用じゃないですよ。これは当日のお楽しみということで」
式さんは、奇妙そうな顔でちょっと首を傾ける。
「お前は何をやらかすのかわからない」
と人を変人みたいに言うので少しへこんだ。
会計を済ませ、俺と式さんは文具売り場を離れる。これでバッチリだ。嗜好性と実用性を半々備えた内容だと思う。
「まて、数が足りなくないか?」
式さんが何気に言った。なるほどいいところに気が付いている。
「その件ですが、残りの2つは千利の実家からもって来ようと考えています。ですから4つ買えばいいんですよ」
ふーん、とつぶやいて式さんはそれ以上尋ねない。「何を?」と言わないところはさすがだ。
俺と式さんはエスカレーターを下る。時間は17時半を過ぎようとしており、にわかに店内がにぎやかになってきた。男どもとすれ違うたびに、みんな式さんの方を振り向く。
「やっぱりなぁ」
かなり優越感。こういう気分は悪くない。式さんとは何度かツーショットになったが、例の事件を追っているときだから雰囲気も満足感もくそもなかった。事件後に「深夜の散歩」に付き合わされたことがあった。ツーショットはいいとして、暗闇に染まるビル群の中をというのは、なんというのか間違っているというのか不気味というのか周囲に対する優越感は皆無に等しい。
外に出た。すっかり暗い。その分、街をいろどるネオンやクリスマスツリーがとてもきれいだ。大通りも活気づいている。
式さんが白い息を吐き出し、やや頬を紅くして言った。
「御上、次はトウコに頼まれたものと夕食の材料か?」
「ええ、一度荷物を車に積んでからその先のデパ地下で買い物します。ちょうどこの時間帯からだと値引きもしているはずです」
「お前、なんか主婦みたいだなー、あいつと一緒だ」
「幹也のことですか?アイツは母親みたいじゃなかったでしたっけ?」
「おまえらどっちも同じだよ。料理ができる分、御上のほうがレベルが高いかも、ってトウコが言ってたぜ」
「いや、あんたら『女性陣』がずぼらなだけだよ。レベルって利用価値のレベルじゃないよなぁ」
と言いかけて、もちろんやめておく。とりあえず式さんはやろうと思えばできる和食の達人だ。問題は橙子師だろう。なんとなく普段の行動からなんでもできてしまう性分に思えるのだが、本人は健全な食生活路線から脱線しており、偏食であることはなはだしく、それでいて美味しいものには目がないという矛盾を抱えて生活している。もちろん料理しているところを見たことがない。
「あれか?料理したら食べ物じゃなくなるオチか」
まあ、ある一定の線引きで料理は苦手なのだろう。まず、あの女性がエプロン姿で台所に立つという姿を想像することはかなりの勇気と困難さがつきまとう。これは黒桐とも意見の一致を見るところだ。
俺は、不毛な想像を振り払った。式さんがそんな俺をみて怪訝そうな顔をしたが、何事もなかったように表情を元に戻して終わりにした。
それにしても寒い。行き交う人たちも寒そうだ。12月といえば一番夜が長いし冷え込みがきついと俺は思う。厳冬期は2月だけれど、このあたりでは12月がもっとも寒い。
「夕食前だけど、なんか小腹が空いたな」
思えば朝、実家に戻って車を運転し、そのまま橙子さんの事務所によって式さんを迎えにいって買い物に来たので何も食べていない。いや、式さんを迎えに行く間に缶コーヒーくらいは飲んだだろうか。
ちょうど通りの一角に「たいやき」の屋台を発見した。クリームとあんこの2種類がある。いいにおいがする。2種類とも買ってみるかな。
「式さん」
となりにいるはずの着物美人に声をかけたら忽然と姿を消している。やばい、まただ。すこし思考時間を短くしないといけないだろう。考え事をしていて彼女の質問がわからず振られたという話は多い。
しかし、幸いなことに式さんはすぐに見つかった。ちょっと大通りを戻ったその外れの一角で小さな女の子となにやら話をしている。俺は駆け寄った。
「どうしました?」
「迷子だ」
と式さんは簡潔に即答した。俺は女の子を見た。泣いてはいないが、その表情は放心していると言ってよい。たぶん5歳くらいだと思う。フリフリの付いたスカートと黒っぽいコートを身に付けている。その姿から育ちがよさそうに思える。
「あっ」
と思わずつぶやいたのは、少女の意識が俺に流れてきたからだ。かなりの不安感と母親の言いつけを守らず歩き回ってしまったためにはぐれたことを後悔する胸中だった。泣かないのは強いからではなく、自分の置かれた状況が理解できず途方にくれていたからだ。
式さんは少女と同じ目線にすると、やさしく頭をなでて言った。
「名前は?」
短いが澱みが無く、響きに透明感があふれていた。
「ルイ・・・」
女の子はポツリとつぶやいた。
「そうか、お母さんとはぐれたのか?」
式さんの声は低めだが、どこまでもやさしい。普段のクールな口調とは明らかに違う。そのなかに含まれる感情の温かさが全く違うのだ。
女の子はちょっとだけ黙っていたが、やがて肯定するように小さくうなずいた。式さんは微笑んで少女の頭をなでて勇気付け、俺に問うた。
「おい、捜せないのか?」
おそらく、俺の能力で母親の居場所を捜せないのかということなのだろう。が、たとえ顔がわかったとしても「捜すものを視る」という能力ではないだけに、それは難しいことだった。実際、捜す事はできるが、それは記憶と残留思念をたどって行くという、時間のかかることになる。
「そうか・・・」
式さんは考え込む。そのクールに考え込む横顔の美しさは表現しがたい。
俺は、「母親を捜す」という点について最善の案を式さんに告げた。
「式さん、もう少し先に行くと交番があります。まず交番に行きましょう。彼女の母親が交番に立ち寄っている可能性が高いです」
デパートなどで迷子を発見したときと考えは同じだ。決まった場所に連れて行くことによって発見を早くしてもらうのだ。捜し歩くのはよほどの心当たりが無い限り適切ではない。そもそも少女が母親とはぐれた場所が判然としない。もしかしたらこの辺りではない可能性もある。
この辺りは商業施設が密集し、車と人の往来が激しいため、3箇所の交番と1箇所の警察署が設けられている。少女の母親もこれだけ暗くなり、見通しが悪くなればやたらと探し回らず、まず近くの交番に駆け込むのではないだろうか。どこかで届けられていれば、俺たちが少女を交番に連れて行けば、母親なり家族なりにすぐに連絡が付く可能性が極めて高い。もし家族と連絡が付かないなら、警察のほうで少女を自宅まで送り届けてくれるはずなのだ。
「なるほど、その通りだ。さすがだな」
式さんはゆっくりと立ち上がり、少女の手をとった。
「ちょっとだけ歩こう。交番に行けばお母さんに早く会えるよ」
式さんの声を受けて、少女は歩き出した。その顔は会った時よりだいぶ落ち着いているように思える。それは式さんが声をかけて安心させ、励ましたからだろう。情の薄れた昨今、いや、まさか式さんがこれほどの一面を俺の前で見せてくれるとは驚くばかりだ。
「おっと、そうだ」
俺は猛ダッシュで「たいやき屋」に寄り、あつあつのタイヤキを6匹購入した。クリームとあんこのヤツとそれぞれ半々だ。
「おまたせ、さあ行きましょう」
「おまえ、何しに行ったのかと思ったら、たいやき?」
「お腹空きませんか?」
と俺は言って、たいやきの入った袋を2人に差し出した。
「まあ、遠慮なく。どうせ橙子さんのお金だし」
式さんは、まず女の子に選ばせてあげる。
「遠慮するな、お腹空いただろ?」
少女は式さんの勧めをうけてクリームの入りのたいやきを取った。式さんと俺も一匹取り出し、3人でパクリ。
全員、頭からだった。
「おいしい」
女の子の表情にようやく笑顔が戻った。放心するくらいの状態で大通りとはいえ、暗くなった空の下でずいぶん心細かっただろう。灯火やクリスマスの飾りが辺りをいくら明るくしても彼女の不安を小さくすることはなかっただろう。そんな少女の様子に気が付いたのは「両儀式」だけだったのだ。
およそ150メートルの移動は5分だけ経過して終着点を迎えた。交番に着くと、俺が事情を説明する。おまわりさんは少女から丁寧に名前を教わり、なにやら書類を作成するとデスクの上にある電話をとった。
ほどなくして問い合わせる声のトーンが高くなり、
「ついさっき西側交番のほうに届出が出ていたよ。すぐにお母さんに連絡を取るそうだ」
とおまわりさんは俺たちに告げた。こうも簡単に見つかるとは幸いだ。交番に来たのは正解だった。
ふと2人を見ると、なんと式さんと少女が互いに手を叩いて喜んでいた。
「すごいの見ちゃったよ」
それからおよそ20分間、俺と式さんは少女と一緒に待った。彼女が不安そうな顔で式さんのブルゾンをつかんだまま離さなかったからだ。
そして、その理由もわかった。交番に現れた少女の母親は着物を着ていたのだ。きっと母親と同じ装いの式さんに安心感を覚えたのかもしれない。
小さな事件はスピード解決した。少女がずっと手を振って俺たちを見送ってくれた。母親と再会したときは緊張感が切れてしまったのか号泣して抱きついたものだった。上品そうなお母さんにもずいぶん頭を下げられた。
去り際、少女の頭をなでて「しっかり手を繋いでおくんだぜ」と言って微笑んだ両儀式の横顔は一生忘れがたい光景になった。
「美しいバラには棘がある」
の代名詞のように思われがちな両儀式。クールな態度で誤解されがちだが、「識」という半身を失い、自分の「生」を実感できず「 」の状態である「器」はある意味純粋だった。邪心や悪意、理由の無い力の行使には容赦が無いが、純真でひたむきな姿には心を開くのだ。
さわやかな心で式さんに振り向いたら、
睨まれていた・・・
「御上、誰にも言うんじゃないぞ」
「えっ、何のことです?」
ボケは失敗した。目が「直死の魔眼」を発動しそうだったので、慌てて絶対に口外しないことを約束する。
「じゃあ、さっさと食材買うぜ。何を作るんだ?」
「歩いて考えましょう」
ガン、と一発右フックをもらいながらも、12月の夜空の下、俺は式さんとメニューを考えるのだった。
(其の参)
まさかデパートの食品売り場まで来てしまうとは思わなかった。ほいほいと着いて行く私も私だが、この男は幹也とは違った意味で本当に手強い。幹也が母親みたいな穏やかさで心を呼び起こす本音を私にぶつけてくるとすると、御上の場合は鋭利でどこか熱い本音を臙条巴感覚でぶつけてくるのだ。いつの間にか臙条を受け容れてしまったように、御上真もいつの間にか受け容れてしまっていた。私もずいぶん人に慣れたものだ。
今夜の献立は一応決まった。白米、イワシのつみれ汁、肉じゃが、ゆでたほうれん草、カブと大根の漬物、アジとマグロの刺身、あとてきとーに惣菜を買うことした。
「ところで、トウコの事務所に炊飯器なんかあったか?」
私は、ふと思い至って聞いた。
「ありましたよ、5年くらい前のヤツです。買ってから一度も使ってないヤツがね」
私はドン引きしたが、間違いなく機能するということだった。あの魔術師は私の食生活についてあれこれと詮索するくせに自分こそ不摂生な食生活を送っていると思う。
まて、そもそも私はトウコが事務所で食事をしている姿を見たことがあったか?たいてい見る光景はタバコを吸っているかコーヒーを飲んでいるかのどちらかだ・・・どちらもだ。
まさかあれだけで生きているわけではないだろう?
惣菜コーナーに来た。御上は少々迷って野菜コロッケと肉団子を選ぶ。なぜそれを選んだのか、いちいち詮索する気はない。
「いやー、本当ならコロッケも手作りしたいところでした」
こいつはめんどーな事を増やすつもりだったのか。当初はすべて「手料理」を予定していたようだが、計算が狂ったとかで(たんに計画に無理があっただけだと思う)料理のいくつかは出来合いになる。それでもお吸い物、肉じゃが、ゆでたほうれん草、刺身は手作りになる。白米は手作り以前の問題だ。漬物はすぐにできるわけが無いので食品を買うしかない。
「じゃあ、お味噌汁と刺身をお願いしますね」
私は、思わず返事をしてしまうところだった。この男の切り出しは唐突と言うかさりげないと言うか、通りすぎる風に近い。
「なぜオレが作らないといけないんだよ。お前が言い出したんだから一人で作れよ」
私は当然断った。買い物に付き合うことは約束したが、この男のとーとつな思いつきに乗る気など毛頭ない。
・・・はずだったのに、私は承諾してしまった。とりあえず幹也がらみとだけ言っておく。
私は、なんとなく自己嫌悪を抱きながら上機嫌でショッピングカートを引く男の後ろを付いて行く。そいつはその売り場まで来ると、なんの躊躇も無くそれをカートの中に放り込んだ。
「ちょっと待て。何を入れた?」
問い正す私に御上は涼しげな顔を向けた。
「これです」
自慢でもするかのようにハーゲンダッツのストロベリーを掲げて見せる。
「おい、今は12月なんだけど。アイスなんか何に使う気だ」
「おや?式さんの好物じゃなかったでしたっけ」
私はめまいがした。
「黒桐がね、式さんはハーゲンダッツのイチゴが好きだって教えてくれたんですよ。よく食べてたって」
あのバカ! 幹也はどういう誤解をしているのかわからないが、私がハーゲンダッツが好きだと本気で思い込んでいるらしい。いつだったか、私とイチゴがどうのこうのという話をしていたのを思い出した。これが夏なら少しは妥協しただろう。だが今は冬だ。しかも雪が降りそーな日だ。ウサギといい、イチゴといい、どういうイメージでそうだと決め付けているのだろうか。人が迷惑しているのがわかっていない。
「オレ、冷たいものは苦手なんだけど」
「あれ、式さんのアパートに泊まったときにハーゲンダッツを出されましたけど12月に」
「あれは、幹也のヤツが勝手に入れておいて忘れた分だ。たまたま他に何も無かったからお前に譲ったまでだ」
「臙条巴にも出したでしょう?」
なぜそんな見たようなことをコイツは知っているんだ。まて、この男は人の記憶を見ることなどたやすいはずだ。残留思念さえ読みとる能力者じゃないか。
「橙子さんから聞きました」
私は呆然とした。なぜトウコが知っているんだ。あの魔術師に告白したことなどこれっぽちもないぞ。
私はハッとした。なんとなく御上にさっきのお返しをされたのではないかと感じたのだ。思い切りカウンターを食らった気がした。
「はっはっはっ、冗談ですよ。橙子さんから聞いたことは本当ですよ。アイスを購入する意味です。これはクリスマス当日に使います。こんなでかいの式さん用なわけありませんよ。それならカップタイプを買いますよ。いります?」
「いるか!」
と言って御上の尻を蹴飛ばしてやった。イラついたことはもとより、してやられた敗北感を認めたくなかったからだ。この男を殺す理由があれば尚よかっただろう。しかし、
「じゃあ、橙子さんの頼まれ物を買って任務完了としましょう」
と全く堪えていない。笑って私に告げる。
「そうそう、もうひとつカートが必要ですね。そのカートは式さんが引いてくださいね」
「なぜオレが・・・」
「えっ、俺に2つ引けと?ムリムリ、たくさん買い込む橙子さんに文句言ってください」
私は、なんだかこの男に逆らう気力がなくなってしまった。コイツはやはり手強い。
私はやけくそでカートを引いた。「幹也がいたらもっと楽しかったなぁ」などとあからさまな声を聞き流しつつ、御上が放り込むインスタント食品やレトルト食品を無感動で眺めていた。
ようやくすべての買い物は終わった。トウコのせいで荷物が多い。私もいくつか手に買い物袋を持っている。御上は私より3つくらい多い。もちろん重量物はコイツが持っている。
外に出た。
「車をこっちの駐車場に移動しておくべきだったかな?まあ、近いからいいいか」
御上がぼやく。駐車場までは300メートルくらいだろう。たいした距離じゃない。たいしたことがあるとすれば人通りの多さだった。大通りも車が渋滞している。視線を流し反対の通りを見ると、ある店の前にたくさんの行列ができている。目を凝らすとケーキ屋だった。私の視線に気づいたのか御上が言った。
「ああ、ご心配なく。ケーキはすでに予約してあります」
とりあえず「違う」と言っておいた。
「そうですか。てっきりケーキをいつ買うのか問われているように見えました」
私はそんな顔をしていたのだろうか? だとしたら自分を殴ってみたくなる。
「ケーキは当日、千利の実家近くにあるケーキ屋さんに取りに行きます。チロルというんですが、大臣賞も取ったこともある千利家御用達のケーキ屋さんなんですよ」
「ふーん」
「本当においしいですよ。味は保障します。当日楽しみにしていてくださいね」
御上は楽しそうに話す。そこのマスターが30代に見えないとか、奥さんがとてもかわいいとかなんとか聞いてもいないことをベラベラとしゃべる。普段より多く話すところをみると、かなりのお気に入りらしい。私は冗談で、
「ふーん、今度連れて行けよ」
と言ったら大変なことになった。
「お任せください、式さま。必ずあなたが満足していただけると自負しています。式さまにお勧めはジャンボイチゴの乗っている定番のふわふわデコレーションケーキでしょう。またはチョコとバナナの絶妙なマッチングが甘さをくすぐるチョコバナナケーキもございます。ですがこだわりはやはりストレートなチーズケーキです。産地にこだわったミルクを使用し、甘さととろけ具合を追求したチロル特製のチーズケーキはこの世のものとは思えない食感を約束いたします。さらに・・・」
と10分ほど秋隆口調でしゃべりまくっていた。最初のほうはあきれた状態で仕方なく聞いていたのだが、いつの間にか口元がほころんでいることに気が付いてしまった。
私の心の変化。「 」のままの心に最初に触れたのは黒桐幹也だった。それを徐々にうめてくれたのも幹也だった。実感できない生が実感できる生へと少しずつ変わってきていることを認めずにはいられない。
次に触れたのは臙条巴だった。とーとつな共同生活が始まってしまったが、私は臙条がぶつけてくる透明で熱い感情がとても気に入ったのだと思う。私の「 」の心に直球で入り込んできたのだ。
御上真はどうだろう。この男は幹也のように私の「 」の心に触れ、臙条のように「 」のなかに入り込んできた。どこまでも直線的な感情と本音を何の躊躇も無く「 」の心へとぶつけてくるのだ。時には大胆に、そして繊細に、たまにとぼけた調子で私の心をかきまわすけれど、まだ完全に生の実感を得たとは言いがたい両儀式の心を揺さぶるだけの力を持っているのだ。
私が、御上真に黒桐幹也と臙条巴の性質を感じ、まるで2人に接するように日常を過ごすことができるのはそういうことだ。
だから、私は幹也と同じように笑って言うことができる。
「おすすめのケーキとやらがオレの味覚に合うことを期待するぜ」
(終幕)
「ええ、ちょっと長くかかってしまいまして、これから戻ります。はっ?その点はご心配なく、夕食は作らせていただきます。1時間ほど待っていてください」
──19時08分──
駐車場に着いた俺は橙子さんに連絡を入れた。予定より2時間ほどオーバーしている。このまま帰るだけなら時間的には問題ないが、なにせ「夕食作ります」と宣言してしまったため、戻ったら食事を用意しなければいけない。
「まー、遅くなっても俺はいいけどね」
橙子さんと幹也が何と言うのか心配だったが、2人とも待ってくれるとのことだった。橙子さんのことだから「もう外食だ」とか「弁当買って来い」とか申し渡されるかとヒヤヒヤした。
「せっかくお前が手料理を振舞ってくれるんだ。遅くなっても私は君の作った夕食をいただくよ」
橙子さんに電話口で実に感動的なお言葉を賜ったのだ。これはがんばらないといけない。
「じゃあ式さん、帰りましょう」
やや眠たそうな式さんを助手席に認め、俺は車のエンジンをかけて駐車場を後にする。
「あれ?」
大通りに出ようとしたらものすごい渋滞に巻き込まれてしまった。ついさっきまでノロノロながら進んでいたのに、いつの間にか流れが止まっている。なんだか怒号とかクラクションが聞こえてくる。
「何かあったな」
直感的に事故を確信した。200m先に交差点があるが、どうやらそこではない。さらに直進したもう一つの交差点で問題が起こったようだった。2分後、サイレンが鳴り響き赤色灯やらがひっきりなしに行き交う。
「やれやれ、最後のほうでこれかよ」
今日、ずっといい言事ばかりだったから、これはその反動かな。とりあえず車はどこにも動けない。万事休すだ。事故の処理が一秒でも早く終わることを願うしかない。なんとか200m進めれば右折して事務所に戻ることができるのに、たった2mも進まない。5分たっても15分たっても動かない。反対車線も同じ状態だ。ラジオをつけるとちょうど事故情報が流れていて、ますます今の状態が当分固定されることを知ってしまう。
「ねえ、式さん」
俺は、助手席に座る着物美人に話しかけた。両儀式はぼんやりとフロントガラスの向うを見ている。
「式さん、どうやらしばらく動きそうに無いようです。通行止めにされてます。これだと歩いて帰ったほうが早いと思います。先に戻っててくれませんか?橙子さんには連絡いれますから」
式さんの反応は緩慢だった。眠そうな目のまま俺を一瞥すると、彼女は右の人差し指でフロントガラスをトントンと叩く。
「えっ?」
「よく見てろ、来るぜ」
なんと10秒後、フロントガラスに水滴が次々と当たりだした。
「あめだ・・・」
「そういうことだ。傘も無いのに雨の中、オレに橙子の事務所まで歩いて帰れと?」
「いえ、めっそーもございません」
俺は、式さんの直感に驚きつつ、降り出した雨によって慌しくなる通りの様子を目に映す。予報だと夕方以降、雨になるということだったが、まさにそうなってしまったわけだ。あわよくば降らずに終わるかなという楽観視は間違いだったようだ。とりあえず買い物中は降らなかっただけよしとしよう。
「うおっ!」
小さく叫んでしまったのは車内のガラスが急激に曇りだしたからだ。ちょっと窓を開けて手を出すと、凍りつきそうなくらいの冷気がまとわりつく。雨が降り出してから一気に気温が下がったようだ。俺はエアコンの温度をもう少し上げた。
突然、式さんがシートを後方に倒し、ゴロンと寝そべった。
「御上、オレは寝るぜ。トウコの事務所に着いたら起こしてくれ」
「寝るんですか?」
「あったり前だ。この状況でオレに起きて何をしろと言うんだ。わるいけど一眠りさせてもらうぜ」
式さんは不機嫌そうに言うと、ものの10秒もしないうちに穏やかな寝息をかき出した。その姿はなんとも無防備だ。いや、年齢相応の女の子だった。
「やれやれ」
俺は、ハンドルにもたれたまま一向に進まないフロントガラスの先を見た。前の車の赤いブレーキランプが寂しげに光っている。楽しい時間は終わったのだ。全てが終了したわけではないが、少なくとも式さんと一緒の買い物は終わった。最初から最後の方まで驚きと新発見の連続だった。まさに変わりゆく日常だ。幹也には悪いけど、今日、式さんが見せてくれた様々な一面は俺だけが出会うことができた「宝物」だろう。
そして、また明日の日常が訪れるように、「気まぐれな美しい殺人鬼」はきっと今後も素顔をちょっと覗かせてくれるに違いない。
「式さん、カゼひきますよ」
俺はジャンパーを脱ぎ、傍らの両儀式にそっとかけたのだった。
──1998年12月22日、19時36分──
師走の寒空から容赦なく水滴が次々と舞う。大通りは渋滞し、車は当分動きそうにない。行き交う人々は白い息を吐きだしながら足早に歩道を過ぎ去っていく。
それでも夜遅く降りだした冷たい雨は、まだ雪に変わろうとはしていなかった。
・・・END
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
あとがき
? 涼です。 買い物編の後編をお送りしました。年内に前・後編に決着をつけることができてよかったです。内容的にはあまり脱線しないようにしました。「こういうのはありえるだろう」というさじ加減だと思います。また、この話はクリスマスへと続いていくのですが、「時間くれ」ですw
空の境界の劇場版もあと六章と七章になりました。普通に考えると年末から新年にかけて公開されるはずです。もう一つ、ふじのんネタを書いていますが、礼園女学園を舞台にした六章を見るまで封印かもしれません。なぜかというと、学園内が判るからです。
なんか「ネコアルク」ネタものを書いてみたくなりました。
ご意見・ご感想があればどうぞよろしくお願いします。
2008年11月9日 ──涼──
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
押して頂けると作者の励みになりますm(__)m
<<前話 目次 次話>>